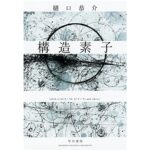いなたくんへ
2010年のジャスミン革命を発端とする一連の民主化運動「アラブの春」は、その背景にSNSなどのネット技術があったことから、インターネットが個人に力を与えることの好例とされた。
Googleの共同創業者エリック・シュミットは、「オンラインでつながること」が我々個人にもたらす力を「第五の権力」と呼んでいる。
情報通信技術の普及が及ぼす最も重大な変化は、国家や機関に集中していた権力が分散して、個人の手に渡ることである。歴史を振り返ると、これまで新しい情報技術が開発されるたび、国王であれ、教会やエリート層であれ、従来の権力者が力を奪われ、人々が力を手に入れた。そして情報や新しい通信方法を利用できるようになった人々は、それまでにない方法で社会と関わり、責任を追及し、より主体的に生きる機会を得たのである。
『第五の権力』より
国家権力は立法・司法・行政、いわゆる三権で統治されている。それに加え、20世紀型の報道機関は、政府を監視する役割を担う「第四の権力」といわれた。(中略)これからの時代は、誰もがオンラインでつながることで、私たち1人ひとり、80億人全員が新しい権力、つまり「第五の権力」を握るかもしれない。
『第五の権力』より
しかしその後の経緯はどうだろう。英エコノミスト誌が『2050年の世界』(2012)で「体制派の権益が拡大するスピードは、それを止めようとする人々の力が拡大するスピードを上回る」と予想したように、国家による技術的キャッチアップが目立って見える。
エリック・シュミットとジャリッド・コーエンの共著『第五の権力』(2013)はまさに、コネクティビティがもたらす「権力」の未来を予想した一冊で、いま読んでも色褪せぬ内容なのでまとめてみた。


私たち1人ひとりが新しい権力を握るかも、とか明るい予言に見せかけて、読んでいくとだんだん雲行きが怪しくなっていく。もしかしたらエリック・シュミット自身も書きながら「あれっ個人が力をもつ…はずだったのに…」みたいな、落としたかった落としどころに落とせなくなったんじゃないかと思ってしまった。
Summary Note
1.「データの永続性」が変えるアイデンティティの未来
2.インフラを握る国家はゲートキーパーとしてふるまう
3.インターネットは分断され、仮想多国間主義が興る
4.コード戦争が勃発し、紛争地域には国際認証監視団が派遣される
5.革命への参加は容易に、そして成功は困難になる
まず最初に、コネクティビティが私たち個人にもたらす未来に触れておく。
本書によれば、私たちのアイデンティティは「オンラインアイデンティティ」を指すようになる。人生の各段階に起こるすべての事実と虚構、失敗と成功が「オンラインの物語」として蓄積され、保存されて永遠に残る。私たちはこうした「オンラインに克明に記録された過去によって、将来を大きく左右され」ることになる。
私たちの世代が、消し去ることのできない記録をもつ、「人類最初の世代」になる。
『第五の権力』より
今までは、オフラインの世界でつくられたアイデンティティが、オンライン世界にそのまま投影されていた。しかし将来私たちは、オンラインでつくり出されたアイデンティティを、オフラインの世界で実際に経験するようになる。
『第五の権力』より
本書によれば、将来的には「18歳未満に作成したものはすべて不問に付すようにな」り、「オンラインに残る若気の過ちは大目に見られるようになる」かもしれない。が、それまでには「まだまだ紆余曲折」を経ねばならない。
子どもがオンラインの行為で将来を棒に振ることを防ぐのは親の責任であり、「性教育よりも先に、プライバシーとセキュリティの教育が必要になる」。
オンラインアイデンティティが重要になるにつれ、下記のような犯罪が一般化する。
- 誰かが他人のオンラインアイデンティティを故意に汚そうとする
- オンラインアイデンティティは「通行証」として大きな価値をもつようになるため、本物または偽のアイデンティティを売買する「闇市場」が出現する
- 銀行口座の詳細からSNSのプロフィールまで、オンラインアイデンティティをまるごと盗み金銭を要求する「仮想誘拐」が一般的になる
これに対して重要になるのがバイオメトリック認証だ。また、オンラインアイデンティティを守るための保険を提供する企業も登場する。
犯罪者に対しては、裁判所命令による仮想アイデンティティの凍結がなされる。凍結されたプロフィールとの接触や交流、宣伝は法律で禁じられ、釈放後は保護観察官にオンラインアカウントへのアクセス権が与えられる。
ちなみにアイデンティティから話は外れるけど、本書は「確証バイアス」にも触れていた。
オンラインの情報源が増えれば、その分確証バイアス(人が意識的、無意識的に、自分のもっている世界観を裏づけるような情報ばかりに目を向ける傾向)が強まるのではないかという懸念も多い。だが、オハイオ州立大学の最近の研究によれば、この効果は、少なくともアメリカの政治情勢には、思ったほど大きな影響を及ぼしていないという。
『第五の権力』より
この予想が楽観的に過ぎたことは、「Alternative facts」の言葉に象徴される2016年の大統領選をみれば明らかである。
それでは、既存の権力を握る「国家」との関係はどうなるだろう。コネクティビティは個人と国家にいかなる力を与えるのか。
いずれにしても国家の野望それ自体は今後も変わらない。 変わるのは、その野望をどのように実現するかという考え方だ。
『第五の権力』より
本書によれば、コネクティビティは個人に「第五の権力」を授ける。例えば「贈収賄や汚職に関する情報を広めたり、選挙違反を報告したり、政府の責任を追及したり、市民は技術を通じて、これまで不可能だった斬新な方法で警察を取り締まる力を手に入れる」。あるいは、「法制度が腐敗しているか、機能していない国でも、悪人はメディアを通じてオンラインで公に裁かれるようになる」。
例えば中国では、ネットを駆使しての政治家の腐敗追及が「人肉検索」なんて呼ばれて流行ったりした。やっぱりネットはすごい!ネットを使えば、政府の悪事はたちどころに暴かれる!
と言ったところでさっそく雲行きが怪しくなる。
しかし政府は、自国内のインターネット設備に対しては、莫大な力を有している。送電塔、ルータ、スイッチといった、コネクティビティに必要な「物理的インフラ」への支配力を通して、インターネットデータの出入り口と経由地点を、政府はコントロールしているのだ。(中略)
民衆が、コネクティビティを通してアクセスできるようになったもの(情報やデータなど)から力を得ているのに対し、国家はゲートキーパー(門番)としての立場から力を得ている。
『第五の権力』より
本書によれば、政府は「情報通信技術をおそれて禁止するより、逆にコネクティビティとデータの力を積極的に利用する場合が多い」。結果として「技術的な対抗策も、ハイテクに精通したほんの一握りの人を一時的に保護するにすぎ」ず、「かつて存在したわずかなプライバシーは、長い間にわたって失われる」ことになる。
もっとも、政府はいたずらに市民を抑圧するわけでもない。本書は、「明るい北朝鮮」とも呼ばれる独裁国家シンガポールの首相、リー・シェンロンの次の言葉を紹介していた。
「インターネットは、ガス抜きにもってこいです。」
『第五の権力』より、リー・シェンロン首相の言葉
本書の予想によれば、未来の政府は多少の批判に目をつぶり、インターネットを通じた不満の発散を許容する。ただし、これは政府が支配する特定のチャネルを通じたものに限られる。
また、重要情報のほとんどを政府内にとどめながら、とるに足らない情報を公開して開かれた政府を謳ったり、配下の政府機関や政権自らの犯罪を公表したりして、点数を稼ごうとする。
本書は政府によるフィルタリングモデルを次の3つの類型にまとめていた。
「露骨型」:
例えば中国がこれにあたる。中国は検閲ツール「金盾」や「グレート・ファイアウォール」を擁し、本書曰く、中国のインターネットは「中国の国家的地位を守る番人にほかならない」。
「及び腰型」:
ネットの自由を求める国民の声に応えつつ、検閲方針の実態は知らせないタイプで、例えばトルコなど。市民社会が成長しつつあるが強力な国家機関が存在する国や、安定した支持基盤をもたないが一方的な決定を下せる集中的な権力をもつ国が、このタイプになりやすいという。
「政治的・文化的容認型」:
法律に基づき、限定的・選択的フィルタリングのみを行うタイプで、韓国、ドイツ、マレーシアなど、さまざまな国に採用される。当局は検閲を隠したり、背後の意図を伏せたりしない。国民の大多数も、安全性や公共の利益のためにフィルタリング方針に同意している。
本書によれば、残念ながら政府が3つめのモデルを採用するのは「市民がきわめて能動的で、情報に通じている場合に限られ」る。「ほとんどの政府が、インターネットが完全に普及するより前に方針を決定することになるため」、「自由でオープンなインターネットを自ら率先して推進しようなどという政府はまずない」。
インターネット技術を用いた国家による権力行使の一例として挙げられるのが、マイノリティへの攻撃である。
例えばISPに命じて特定のキーワードを含むサイトをすべて遮断・閉鎖させることで、自国のインターネットから、集団に関連するコンテンツを消し去れる。
本書は中国政府が「少数民族ウイグル族にこのような抑圧を加える可能性は十分ある」とし、検閲を行うことで、主流民族の若い世代はマイノリティ集団の存在にも、それにまつわる問題にも、ほとんど気づかずに育つだろうとする。
マイノリティ集団を対象とした電子的隔離政策は、今後あたりまえになるだろう。 国家はそれを行う意思をもち、それを可能にするデータへのアクセス権をもっている。
『第五の権力』より
国家権力への対抗では、ジュリアン・アサンジのウィキリークスのような内部告発サイトがある。ただし、こうしたプラットフォームは次のような厳しい条件を満たさねばならず、作り上げることは並大抵ではない。
- 地政学的に意味のある、新しい、多くの場合大量のリークを頻繁にアップロードして、世間の注目を浴び続ける
- 組織を代表するカリスマ的リーダーが「人間避雷針」として批判を一手に引き受ける
- 情報提供者を保護する能力を見せつけて、情報提供を迷っている人の背中を押す
- 情報提供者、組織のスタッフ、一般人が、(互いに身元を知られずに)リークされた資料をとり扱えるようにし、複数の国の当局による遮断を回避する
適切なプラットフォームを構築できたとしても、「情報提供者は、自らの暴露によって最大限のインパクトを引き起こせる組織、かつ最大限の保護を与えてくれる組織に自然と集まる」ため、同様のものが世界に同時に5つ以上併存できる可能性は「ないに等しい」という。
未来の世界にもアサンジたちは存在するが、支持基盤は小さいままにとどまるだろう。
『第五の権力』より
「国家対国民」の関係では国家が優位に立つ、と本書は示唆するが、面白いのはその先の「国家対国家」の関係も示している点である。国家がインターネットを使って自国の支配を強めるとき、他国との競合関係が生まれ、インターネットの分断を招くかもしれない。
おそらく10年先には、各国が「インターネットを使うかどうか」ではなく、「どのバージョンのインターネットを使うか」が、最も重要な問題になるだろう。
『第五の権力』より
政府がフィルタリングなどによってインターネットを規制すれば、グローバルであるべきインターネットが、「国ごとのネットワークの寄せ集め」と化す、という懸念が生じる。そうなれば、やがてワールドワイド(世界規模の)ウェブは砕け散り、「ロシアのインターネット」や「アメリカのインターネット」などが乱立するようになるだろう。
『第五の権力』より
こうした一連の変化は、当初ユーザーにはほとんど感じられないが、時間とともに蓄積していき、やがてインターネットをつくり替えるだろうという説もある。「インターネットのバルカン化」(Balkanization)、つまりインターネットの世界に、一種の国境が設けられてしまうのではないかという懸念である。
『第五の権力』より
「インターネットの分断」は未来の話では決してない。山谷剛史著『中国のインターネット史』(2015)では、中国におけるインターネットの歴史を黎明期から時間順に整理しつつ、近年すでにワールド・ワイド・ウェブから独立しつつあることを明らかにしている。


本書『第五の権力』は、検閲というよりは言語・文化の同質性から人がオンラインでも自国文化圏にとどまることや、国内閉鎖的なインターネットの出現を予想するが、『中国のインターネット史』で語られる現状はこれと全く符合しており必読である。
『第五の権力』ではその先の話として、当該国のネットにアクセスするための「ビザ」の義務化を予想していた。例えばユーザは登録と一定の条件への同意が求められる。
さらには、他国のネットにアクセスできない、仮想世界で自由を奪われた人による物理的な亡命「インターネット亡命」が起こるという。
当初ワールドワイドウェブとして始まったものは、だんだん現実世界そのものに似てくる。それは無数に仕切られた、多様な関心を内包する世界だ。
『第五の権力』より
国家間の関係では、イデオロギー的・政治的な連帯意識をもとに、国家や企業が正式な同盟を結び協力する「仮想多国間主義」も予想されている。
これらの国は、共通の価値観や地政学をもとにウェブを「共同編集」する。これは大まかな文化的合意や、共通の反感に基づくもので、宗教的マイノリティへの反感や、特定地域に対する見解、歴史的人物についての文化的解釈などである。
あるいは「商業的利害、なかでも著作権と知的所有権の問題を中心にして、新しい同盟が結ばれる」可能性も示唆する。本書によれば、「著作権法と知的所有権法の大半が、いまだに物理的商品の概念を中心としている」。
実利といえば、安全保障をきっかけとした同盟も現実的だ。本書曰く、「どこかの独裁政権が監視国家の構築に成功すれば、その「成果」を必ずほかに伝授しようとする」。「例えばベラルーシやエリトリア、ジンバブエ、北朝鮮など、独裁主義的で」「「のけ者扱い」されている諸国にとっては、共通の検閲、監視戦略をもち、技術を共有する、独裁主義国のサイバー連合に参加しておいて損はない」。
私としては、中国の社会信用システムが今後(日本を含む)周辺国にどう広がっていくかは見ものである。
同盟関係ではなく敵対関係においてもインターネット技術は重要になる。サイバー攻撃である。
サイバー攻撃の定義について本書は、米国政府元テロ対策担当責任者リチャード・クラークによる「国民国家が損害や混乱を与える目的で、他国のコンピュータやネットワークに侵入する行為」を採用している。
その特徴は、「攻撃の帰属を確定するのが非常に困難なため、被害者は手がかりをほとんど得られず、犯人は疑惑が高まっても逃げ切れる」というものだ。
サイバー攻撃が普及した未来において、国家間の争いはどのようなものになるだろう。
スタクスネットのような物理攻撃の事例もあるが、本書は「サイバー攻撃がそこまでエスカレートすることはほぼないと、楽観している」。理由は「過激な攻撃を行っても、それに輪をかけて激しい反撃を受けるだけだからだ」。
と言いつつ読み進めてくと例によってその雲行きは怪しくなるんだど、本書は基本的には、サイバー戦争とは「企業秘密の不正入手や、極秘情報へのアクセス、政府システムへの侵入、偽情報の流布といった」「諜報目的で行うもの」という立場だ。
本書によれば、コード戦争(Code War)は冷戦(Cold War)の特徴を引き継ぐことになる。
- 世界の主要国が、ある面では一触即発の膠着状態に陥りながら、別の面では何事もなかったように経済的、政治的前進を続ける
- 言論の自由や開かれた情報、自由主義といった問題をめぐって、イデオロギーの断層線がくっきり現れる
- 代理戦争も、デジタル新時代の闘争で息を吹き返す
- 一般市民はコード戦争に関与することも、気づくことも、直接被害を受けることもない
一方で、過去の冷戦とは異なり、二極間の争いにはならず、「イランやイスラエル、ロシアといった、技術に精通した強力な国々を巻き込む、多極的な闘争になる」と予想する。
このために本書は、「小規模な軍隊しかもたないが技術部門が強力な国家が、これからの強国になる」と考える。具体的にはエストニア、スウェーデン、フィンランド、ノルウェー、チリが挙げられていた。
他方、サイバー戦争能力を開発しようとする国にとって、資本供給国の選択は重要である。資本を受け入れる決定を下せば、供給国の「オンライン影響圏」に組み込まれることになるためだ。これは前述の「仮想多国間主義」の構築にも関係するだろう。
実際に紛争が起こった場合には、本書は「相手のデジタルマーケティング能力の破壊」が重要になると予想している。
紛争当事者の主張が互いに矛盾することはよくあるが、これを正当化するのがマーケティング能力であるためだ。「未来の戦争では、データ管理(紛争地帯から発信されるコンテンツの編集、インデクシング〈索引づけ〉、順位づけ、認証)が、技術へのアクセスに次ぐ重要な課題になる」。
とは言え、互いに矛盾する主張がそのまま氾濫すれば、それぞれの主張の価値は下がってしまう。外部の観察者は、紛争を理解するには誰に話を聞けばいいのか、誰を支援すべきか、どのような形で支援すべきか、といった見極めができない。
そこで本書は、赤十字のような中立的機関として、国際的な認証監視団が登場すると予想する。もっとも、信用と責任の重い仕事であり、悪用の可能性が必ず付きまとうため、彼らも「国際機関をむしばむ汚職と無縁ではいられない」。
(本書、ホントにいちいちネガティブなオチがつくんだよね…)
国家同士の争いを紹介したが、再び対国家権力に話題を戻そう。革命である。本書によれば、コネクティビティの普及により「革命がかつてないほど簡単に、そして頻繁に芽吹くようになる」。
本書は新しい革命運動の特徴が次のようなものになると予想する。
- より大勢の人に呼びかけやすくなって参加者が大幅に増えるが、新しい主義主張が掲げられることはほとんどない
- いつどんな方法で反乱を起こすかを市民がより自由に選べるようになり、「パートタイム活動家」や「匿名の活動家」が増える
- 一日中ネットを徘徊し、ただスリルを感じるためだけにオンライン抗議運動に参加し、扇動する「革命ツーリスト」なる集団も現れる
人々が容易に参加できるからこそ、革命を指導する側は、参加者の関心の高さや本気度が測りにくくなる。SNSでの活動は、大衆の支持があるとの過度の自信を組織に与えるが、それは幻想かもしれない。
指導者は、運動が民衆の幅広い支持を得ているのか、それとも内輪の声が反響しているだけなのかを戦略的に判断し、新しい参加者の品質管理を行い、彼らの期待をコントロールしながら、有効に活用する方法を見つけねばならない。
しかしながら、コネクティビティによる運動のペースの加速は「組織や思想、戦略、リーダーが生まれるまでの懐胎期間が非常に短く」し、有力なリーダーの出現を困難にする。
組織は「政府の行政官に根気強く離反を呼びかけるといった、困難だが戦略上重要な仕事をおろそかにするようにな」り、「性急で軽率な行動に走り、革命運動の暴走を防ぐ仕組みを自ら壊してしまう」。
もし革命が成功できたとしても問題はある。コネクティビティにより多くの大衆が蜂起に参加するが、革命が終結すると彼らは「政治プロセスからは突然締め出されたと感じるように」なってしまう。このとき、革命後にすぐ国民の期待に応える能力を持つ新政権は少なく、革命後の社会に円滑に移行できないかもしれない。
本書は「技術はあらゆる当事者に力を与えるが、小さな主体には並外れて大きな影響力を与える」として、「仮想国家」の出現を予言する。
例えばクルド人などの抑圧された民族が、「新しいドメインを登録し、サーバーを中立国か支援国に置き」、「クルド人の仮想コミュニティは選挙を実施し、省庁を設置し、基本的な公共財を提供し、独自のオンライン通貨さえ使用するようになる」。
なるほど、イスラエルみたいにうまく土地を獲得できた例もあるけど、そうでない場合にも、仮想空間に拠り所を創ることはできるわけだ。とは言え本書は例によってネガティブな指摘も忘れない。
現実世界で国家的地位を得ようとする分離主義勢力の取り組みが、一般に本国政府に厳しく弾圧されるように、仮想独立をめざす集団も、同様の激しい弾圧を受けるだろう。(中略)
大がかりな反撃に対抗できるだけの資源や国際社会の支援を得ている分離独立運動は、現状では皆無に近い。オンラインでの建国宣言は、反体制色の強い地域に限らず、どんな地域でも反逆行為と見なされるだろう。野放しにしておくには、あまりにも危険な動きだ。
『第五の権力』より
革命から話は外れるけど、「仮想国家」に似た話として、災害時の迅速な復旧を趣旨とした「仮想政府」「仮想省庁」のアイディアも紹介されていた。データや行政サービスをバックアップとして仮想化するというものだ。
将来は個人情報のバックアップをとるだけでなく、「政府のバックアップ」までとれるようになるだろう。新しい復興のプロトタイプでは、仮想機関が物理的な機関と並行して存在し、必要な場合にバックアップとして機能するのだ。(中略)
省庁を収容する物理的な建物を建て、そこで記録を保管し、サービスを提供する代わりに、情報をデジタル化してクラウドに保存し、政府機能の多くをオンラインプラットフォームで提供すれば、たとえ都市が津波で破壊されても、すべての省庁が物理的に再建されるまでの間、一部の機能をオンラインで提供し続けることができる。(中略)
仮想機関が記録を保存してくれるという保証があるからこそ、事業主は賃金を支払うことができ、国内外に暮らす市民のデータベースは維持される。おかげで地元住民は復興プロセスに主体性をもって取り組めるようになり、災害や紛争のあとに起こりがちな無駄や汚職も軽減されるだろう。政府が崩壊し、戦争で物理的インフラが破壊されても、仮想機関は残るのだ。
『第五の権力』より
これは有望なアイディアと思った。実際にエストニアなんかは国民データや政府機関の仮想化を進めている。もっとも、エストニアの動機は「災害」というよりは「隣国への恐怖」だったりするが。
仮想化するとハッキングリスクも増すように思うが、そのあたりは今後起こるかもしれない侵攻の推移を確認したい。
2008年の南オセチア紛争で、ロシア軍戦車部隊や空爆機がグルジアに投入される直前、グルジアの政府や都市に対して大規模なサイバー攻撃が仕掛けられた。
サイバー攻撃が物理攻撃に用いられることはほんとどなく、基本的には諜報用途である、という本書『第五の権力』の立場は紹介した通りだ。が、その予想とは裏腹に、本書が予想する「世界初のスマートな反政府運動」は穏当でない。
この運動はおよそ次のように推移する。
- 反政府運動を宣言しないうちから、国防の実質的な基幹である政府の通信網を攻撃する
- 海外の協力的な政府に密かに接触して、ワーム、ウイルス、バイオメトリック情報などの必要な要素技術を入手し、内外から自国政府の無力化を図る
- 政府が復旧を急ぐなか、反政府軍は政府のインターネットに侵入して関係者に「なりすまし」、ネットワークのプロセスをさらにかく乱させる(重要なバイオメトリックデータベースに侵入し、政府官僚のアイデンティティを盗んで彼らになりすまし、オンラインで偽の発言や不審な購入を行うなど)
- とどめとして、送電網など物理的インフラを攻撃して操作し、国民の怒りと非難の矛先を政府に向ける
「スマート」な反体制運動は、銃撃戦もなく、たった3度のデジタル攻撃だけで大衆に反乱を起こさせ、政府の不意を突くことができる。そしてこの時点で反体制派は軍事攻撃を開始し、第2の物理戦線を開く。
『第五の権力』より
サイバー攻撃「のみ」で損害を与えることは確かに少ないかもしれないが、現実世界の攻撃との連携を考えれば、その脅威が深刻であることに変わりはない。また、本書はこのような攻撃を「反政府運動」の文脈で書いてはいたが、国家間戦争でも同様のプロセスが用いられるかもしれない。
以上、ちょっと長くなっちゃったけど、「権力」にフォーカスして『第五の権力』で述べられた未来をまとめてみた。
「オンラインでつながることが我々個人にもたらす力」としての「第五の権力」の言葉は、本書では一か所しか登場しない。キャッチーなフレーズなので邦題に使ったんだろうけど、本の中身を代表する言葉ではないような気が。ちなみに原題は「The New Digital Age」。
コネクティビティは個人やマイノリティに力を与える、と口当たりの良いことが書かれつつ、実際に読んでみると国家権力に勝てる気がしないのは私だけかな。
ただ、エリック・シュミットがこういう予想を描くというのは意外だった。Googleはもっと個人の力を信じている気がしたので。だからこそ、本人的にも書いてて不本意な未来が視えちゃったのでは、と思ったりした。
エストニアの例や、サイバー攻撃を積極的に使うロシアや、管理システムを創り上げる中国や、本書で予想される未来が世界のあちこちで実現しようとしている。その未来がどんなものになるのか、引き続き確かめていきたい。