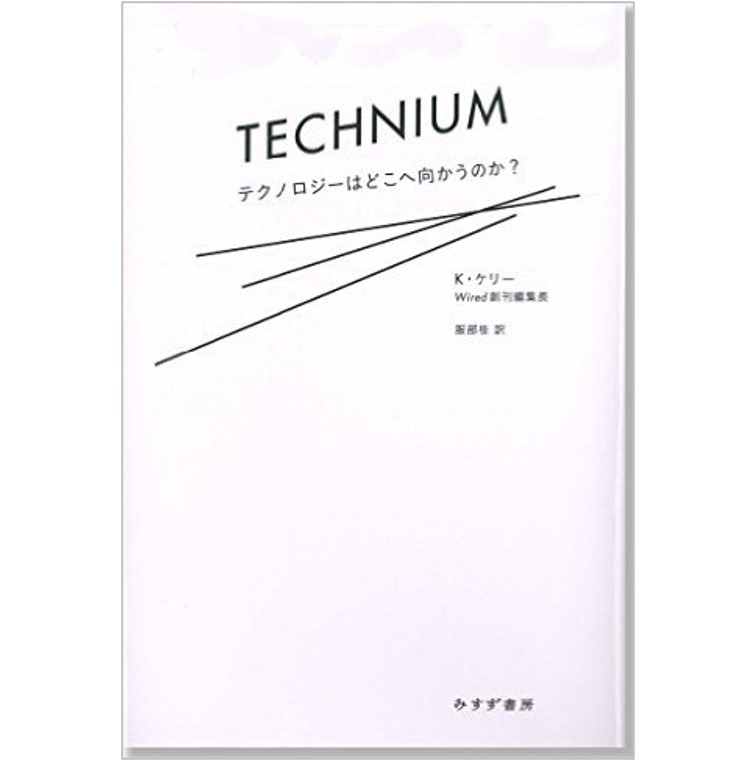いなたくん
生命を「自己生成可能な情報システム」とみたとき、霊長類は8つの遷移を経て、分子から進化してきたことがわかる。この観点でさらに進化を追うと、情報システムとしての生命は言語の発明を介して、「印刷」や「インターネット」を含む「テクニウム」に進化してきたことになる。生命の進化形がテクノロジーであるというのだ。こう主張するのは、WIRED創刊編集長ケヴィン・ケリーの『テクニウム』(2014)だ。

本書はさらに、生命の進化をアナロジーとしてテクノロジーの進化の原理の解明を試みる。テクノロジーの進化を決めるものはいったい何か。
テクノロジーの未来には、偶然が決めるいくつもの道筋があるのだろうか。それともテクノロジーは、決められた1本の道筋に沿って歩んできて、この先もその道を辿るのか。本書が提示する仮説は後者で、時計を巻き戻してやり直しても、同じ結果が得られるという。
原理がわかれば、未来を「正しく」予想できることになる。本書の仮説はテクノロジーの未来を考える上でも重要であるので、これについて紹介する。
Summary Note
地球にヒトが誕生したことは必然である(本書より)
- 進化は「適応」「偶発」「必然」の3つの力により推し進められる
- 進化は偶然の積み重ねだが方向があり、ヒトの誕生は「必然」だった
テクノロジーの進化もまた必然に沿う(本書より)
- イノベーションには事前に決められた固有の順番があり、必要な条件が全て揃ったとき新しいテクノロジーが生じる
- 時計を巻き戻してもやり直しても、同じ抽象系のテクノロジーが顕れる
- テクノロジーの進化は「意図的開放性」「歴史的偶発性」「構造的必然性」の3つの力が形作る
- テクノロジーの方向性や傾向は、発明した人間からは独立であり、発明家は起こるべくして起こる発明を伝えるパイプ役に過ぎない
進化に方向性があり、未来のカタチに「正解」があるならば、未来予測によりこれを探すこともできる
テクニウムの進化を考えるにあたり、著者は再び生命の歴史に立ち返る。
著者が検証するのは、いまある生命のカタチが果たして「必然」であるのかどうかだ。我々人間は、地球誕生以来の様々な偶然の積み重ねでこの地球上に発生した。もし時計を元に戻して再びやり直しても、ヒトは地球に現れるのか。本書は生命のカタチを決める2つの制約を挙げる。
原子の組み合わせ方は無限にあるが、重力をはじめとする物理法則や、幾何学に基づく効率に従うと、実現可能な形態は制限される。これが「負の制約」だ。本書によれば、体重や新陳代謝など地球上の生命を形作る性質は、「負の制約」の影響により必ずある範囲に収まるという。
本書はいくつもの例を挙げるが、とりわけて「必然」の形態なのがDNAだ。本書はDNAに関して、分子生物学者スティーヴン・フリーランドとローレンス・ハーストの実験を紹介する。コンピュータ上で遺伝子コードを無秩序に発生させ、化学的に成り立ちうる2億7000万の候補から、誤差発生の少ない順に格付けしたというものだ。
この試行は1000回以上繰り返され、効率性の分布は典型的な正規分布となったという。そして本書によれば、「その遥かな端に位置するのが、地球にあるDNAだった」。
この実験は、DNAが可能性のあるコードの中でも最も効率的な自己増殖可能な構造であること、これが負の制約に基づく「必然」であることを示唆している。

複製するDNA(Wikipedia)。ちなみに本書は物理的制約から
ケイ素生命体の存在可能性を否定的に見ており、ARMS好きは要反論。
進化は「負の制約」の幅の中であれば完全にランダムなのか。本書によれば、突然変異の中にはあまりに起きやすいものがあるという(自己優先ループ)。
本書が挙げる例の1つが「眼」だ。この「生物的カメラ」は網膜、レンズ、瞳孔の3つの部品が完全にまとまることで機能するため、奇跡とも呼ばれる。
ところが、この奇跡的な光学構造はある種のタコ、ナメクジ、海洋環状生物、クラゲ、クモの別系統の動物たちにも見られ、しかしこれらの共通の祖先は眼を持たないという。それぞれが独立して「眼の獲得」という進化を果たしたことになる。
6度も独立して同じ進化が起きたというのは、奇跡を超えているのでは、というのが本書の投げかける疑問だ。
まるで進化があるデザインを創造したがっているように見える。(中略)生命は眼球を作りたがっている。

Wikipediaによれば50~100回ほど個別に進化したとされる眼。
他の生き物の眼を参考掲載しようとしたけど思ったよりグロかったので、
(たぶん)素敵なお姉さんの眼で勘弁して下さいね。
(画像:The Mechanic Eye / bogenfreund)
系統の異なる生命が個別に同じ形状を獲得することを「収束進化」と言う。本書は眼のほかにも、羽や、反響定位、二足歩行、植物の食虫性、浮き袋など、多くの例を挙げている。これらの事例から本書は、生命の進化には、「遺伝子結合と代謝経路における自己組織化する複雑性が生み出す正の制約」があるとする。
生命の進化の過程は、現在の教科書で正統とされているような、宇宙の中での無作為ではないと主張する。進化やその拡張型としてのテクニウムはむしろ、物質の性質やエネルギーにより決定される固有の方向性を持っている。この方向性によって、必然的に生命の形が作られる。
本書は進化の創造を推し進める力を、次の3つにまとめている。
- 1.機能的適応性
- 2.歴史的偶発性
- 3.構造的必然性
生命は「負の制約」による制限の範囲で、淘汰に基づく機能的適応と、偶発的におこる突然変異の歴史の連続を経て進化する。しかしながら大きな流れにおいては「正の制約」、つまり「自己組織化する複雑性の持つ内的な慣性」が、必然的な構造を決める。
本書は、時計を巻き戻してやり直しても、細部は異なるかもしれないが、巨視的には必然的な構造が顕れると主張する。
この「時計を巻き戻す」について、ミシガン州立大学の実験も紹介されていた。シーケンシング技術と遺伝子クローニング技術により細菌の進化を何度も再現する実験だ。実験では、進化を何度行っても、正確な遺伝子コードは異なるものの進化系統は収束し、表現形(細菌の外観)としては同じものが現れたという。
*
生命が偶然なのか必然であるかは長く議論される問題だが、本書はこの問いに対して「生命は必然的な不可能」と答えている。太古の海を漂う元素が人間に辿り着くのは、まさしく不可能な確立である。しかしながら進化は方向性を持つため、やがて必然的に人間までたどり着く。素晴らしい表現だと思う。

Evolution of the Human / tmkeesey
本章の中で一番の驚いたのはDNAだ。私は人間について、数ある可能性の中の1つが偶然進化できただけ、と考えていた。DNAについても同様だ。ところが本書を読むと、DNAは、自己増殖能力を考えれば宇宙の中でも最も効率が高く、我々は得るべくしてDNAを得たことがわかる。本書は、宇宙人がいたとしても、彼らはDNAとほぼ類似したものを持つはずだと指摘していた。
そして情報システムとしてのDNAは、やがて細胞や身体を獲得し、ヒトに進化して「言葉」を生む。言葉を端に発するテクニウムの進化にも方向性があるのか、というのが本書の最大のテーマだ。
本書はテクニウムについても、生命の進化と同じように「必然」があると考える。我々が普段手にするテクノロジーは、生まれるべくしてこの世に現れたのだ。
電話の発明者グラハム・ベルと、同日に特許出願したエリシャ・グレイの逸話は有名だ。グレイは特許庁への申請がベルに2時間遅れ、電話の発明者の名誉を逃した。グレイの身になってみるととても悔しい。が、本書はこの事例について、ベルとグレイよりも3年前に少なくとも3人が実際に動く電話を作っていたことを明らかにする。
電話はベルやグレイ、そして上記の3人の発明者がいなければ、この世には存在しなかっただろうか。本書は、彼らのすぐ後代に控えたエジソンや誰かしらが、いずれは電話を誕生させただろうと指摘する。
電話は、グラハム・ベルや、特定の発明者がいたからこそ生まれ得たのだろうか。それとも電話は20世紀という時代に生まれるべくして生まれ、その生みの親が誰であるかは実は大きな問題ではなかったのではないか。

グラハム・ベルの電話の特許の図面。右下にベルのサイン。
(米国特許第174,465号,1876/2/14出願)
本書はベルの事例だけでなく、黒点の発見、アドレナリンの分離、電信、対数、タイプライター、アルミニウムの電気分解、映画、などなど数多くの「同時発明」の事例を紹介していた。原子爆弾を実現にする基本公式は、第二次大戦下で各国が機密として並走研究していたが、7つの国でそれぞれ独自に「発見」されたという。
本書が紹介する中でも重要な研究となるのが、考古学者ジョン・トロエンによる有史以前のイノベーションの分析だ。
トロエンは有史以前に起きたイノベーションのうち、アフリカ、西ユーラシア、東アジアの3つの地域で共通して起きたものを数えた。その結果、53のイノベーションが共通して、かつ各地域で独立して発明されていたことがわかった。
注目なのは、53のイノベーションが生み出された順番だ。3つ地域間で比較すると、相関係数は0.93という高い値を示したという。つまり、当時交流のなかった離隔した3つの地域で、53のイノベーションが、ほぼ同じ順序で起こされていたわけである。
この研究の結果から本書は、イノベーションやテクニウムには事前に決められた固有の順番があるとする。
つまり、それ以前のテクノロジーによってすべて必要な条件が揃えられたときに、新しいテクノロジーが生じるということを意味しているだけなのだ。「必要条件となる知識や道具が整ったときに、発見は事実上必然となる」と、同時に起きた発明を研究した社会学者のロバート・マートンも言っている。
本書は、あまりに未来的で先を行き、常識的でない発明は、基本的な材料や受け入れる市場、正しい理解がないため、環境が追いつくまでは成功できないと指摘する。例えばタブレット型の無線通信表示端末はiPad以前にも発明されていたが、早すぎたのか、今日まで続くことはなかった。

シミュレーションゲーム「エイジ・オブ・エンパイア」の進化図。
本作は、暗黒・領主・城主・帝王の4つの時代が設定され、
時代を進めることでできることが増えるようになる。
このとき、時代を進めるには旧時代において必要なテクノロジーを揃えねばならい。
例えば「城主の時代」に進むには、その前に「領主の時代」に
兵士育成所、市場、鉄工所のテクノロジーを得ていることが必要となる。
本書は「テクノロジーも必然であり、その進化も生物と同じように収束していく」と考える。それではテクノロジーを形作るものとは一体何か。著者は次の3つの力を提示する。
- 構造的必然性:あらかじめ定められ展開する牽引力
- 歴史的偶発性:過去の引力としてのテクノロジーの歴史
- 意図的開放性:社会の集団的自由意思、我々の選択
「構造的必然性」は、先に述べた「テクノロジーの順番」だ。ある条件が揃えば、テクノロジーは必然として次の段階のテクノロジーを生む。これは生命における「収束進化」に対応する。
ただしそのディテールは一定でない。本書によれば、スペースシャトルの部品は鉄道輸送時にトンネルを抜けられるサイズとされたが、近代の鉄道の幅はローマ帝国時代の馬車の軌道に基づくことを指摘する。つまりスペースシャトルは、遥かにローマ帝国の影響を引きずっている。これが歴史的偶発性だ。
時計を巻き戻してやり直すと、あるテクノロジーの仕様や表現方法は、もしかしたら違ったものになるかもしれない。しかしテクノロジーの抽象系は必ず決まった順序で歴史に出現することになる。本書は発熱電球にたとえて、次のように述べている。
電球の形状が、タングステンのコイルが楕円形の真空の管に入った形なのは必然ではないが、電気式の白熱電球は必然なのだ。
テクノロジーを形作る3つの力と生命の自然選択に働く3つの力とを比べると、次のようになる。

生物的進化とテクノロジー進化の三連構造(本書掲載図を引用)
3つめの力「意図的開放性」は、生命の「機能的適応性」に対応する。テクニウムの進化が生命のそれと異なるのは、テクニウムにはそれを生み出す人間の意図が働く点だ。ただし本書は、テクニウムが進化し人間の手を離れれば、その影響もいずれ失われると予想している。
ずいぶん長くなってしまったけど、以上が本書の述べる仮説だ。生命とは「必然的な不可能」であり、ありえないような偶然が必然的に積み重ねられ、今に至る。時計を巻き戻しても、細部が異なるかもしれないが、必ず同じような進化が起こる。それはテクニウムでも同様で、時代の段階が進むごとに、生まれるべき発明は生まれるべくして発明される。
本書はテクニウムが生命の延長であり、言語を介して発展したと考えている。
生命がテクニウムを生じる水準の言語を操るまで進化したことも、歴史の必然だ。歴史をやり直しても必ず知性は発生し、それは必ず人間のカタチをしている。その時間軸の人類もまた宇宙船をつくり、インターネットを生み出す。

Rolling Rebellion Sparks in Seattle to Defend Internet & Stop the TPP / Backbone Campaign
もし未来のカタチが完全な偶然に支配され、これを縛るものが物理法則しかないとすると、未来を予想することは非常に困難な仕事だ。「ありえない可能性」は排除できても、ありうる未来は偶然の数だけ多くなるから、結局のところ起こるまでわからないことになる。
ところが本書は、これまでの生命の進化やテクニウムの歩みは「必然」であるとする。ということは、未来のカタチには、少なくとも大まかな「正解」があり、予測を突き詰めてこれを追い求めれば、正しい未来予測をすることも不可能ではないことになる。これは心強い仮説だ。
本書は「複製する分子」から「インターネット」まで続く、生命とテクニウムの進化の歴史を振り返ってきた。それでは今後テクニウムの進む方向とはどこなのか。本書予想に基づくテクニウムの未来、テクニウムのもたらす未来は、次の記事で考えてみる。
ところで本書は、イノベーションやテクニウムの順番には固有の決められた順番があるとした。すると、これを生み出す人間とは一体何者なのだろうか。
テクノロジーが普及したとき、「実は私が先に発明していた」「私が真の発明者だ」と名乗る人物が出てくることは珍しくない。おそらく本当にそうなのだろう。ベルやグレイが電話の発明をする前に、すでに3人が動く電話を作っていたことは本書の紹介する通りだ。
しかしその時間軸における「真の発明者」が誰であれ、イノベーションの順序が予め決められたものならば、その人の役割とは一体何なのだろう。
これについて本書は明確に次のように述べている。
このテクノロジーの発明には方向性や傾向があるということだ。その傾向とは、発明した人間からは独立したものだ。
発明家というのは起こるべくして起こる発明を伝えるパイプ役ということになる。誰でもとは言わないが、誰もが発明家になりうるのだ。
「パイプ役に過ぎない」とはなんだか身も蓋もなく聞こえてしまう。ただしその一方で、イノベーションの「抽象系」の順序は必然として定められているものの、その「表現型」は、生物であれば偶発性、そしてテクニウムであればこれを生み出す人間の手に委ねられている。本書は次のようにも語っている。
誰でもティーンエイジャーになることは必然的だが、どういう10代になるかは(中略)その人の自由意思による選択に支配される。