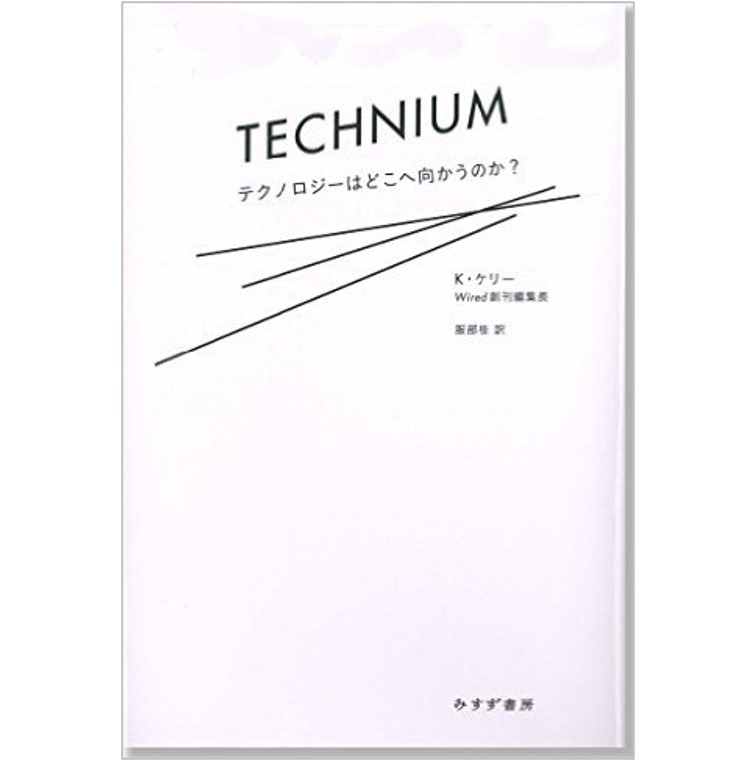いなたくんへ
オーストラリアで、原始的な言語を用いる鳥類が発見されたそうだ。クリボウシオーストラリアマルハシと呼ばれる鳥で、高い社会性で知られ、音の組み合わせでエサやりや飛翔などの意図を伝えるという。英セクスター大とチューリヒ大の発見。人間以外ではイルカも言語を持つとされるけど、鳥も言葉を使うのね。
テクノロジーの歴史における最初の特異点を「言語の発明」とみるのは、WIRED創刊編集長のケヴィン・ケリーだ。そればかりか氏は著書『テクニウム』(2014)で、言語の発明が「生命の進化」と「テクノロジーの自己増殖」とを結んだと述べている。
本書によれば、テクノロジーの進歩の起源は、我々生命の進化や、さらにはビッグバンにまで遡る。そして染色体や細胞から微生物、ヒトへと続いてきた生命の系譜の、次なる進化のカタチとなるのが、テクノロジーの集合である「テクニウム」であるとする。

テクニウムが生命の延長という仮説は、テクノロジーに留まらず生命の未来を占う上でも重要になる。本書の仮説について紹介したい。また本書はこの仮説を下敷きにして、テクノロジーの進化の原理と、「その先」の方向性をも示唆しており、これらについても紹介していく。
Summary Note
生命の進化の系譜はヒトから「テクニウム」へと移る(本書より)
- 生命を「自己生成可能な情報システム」と捉えた場合、「単一の複製する分子」から「霊長類」まで8つの大きな遷移が見られる
- 「テクニウム」もまた「自己生成可能な情報システム」として、言語の発明以来段階的に発展してきた
- 遺伝子以上に早く適応・伝達が可能な言語は、生命の六界とテクニウムとの進化を繋ぎ、テクニウムにとっての最初の特異点となった
本書は、「そもそもテクノロジーとは何なのか」という疑問を元に、テクノロジーの本質を紐解き、未来を探る。そこで明らかにされるのは、我々生命と、テクノロジーのに基づくシステム「テクニウム」とが、進化の系譜の上で連続であるとする仮説だ。ところでテクニウムって何だろう。
本書によれば、「テクノロジー」という言葉は、1882年にゲッチンゲン大学経済学教授ヨハン・ベッグマンが産業革命による機械製品の普及を論じるために使ったドイツ語「Technologie」からきている。そのさらなる語源はアリストテレス『修辞論』に初出する「Technologos」だが、その正確な意味ははっきりしないそうだ。
テクノロジーが個別の方法や装置を示すのに対し、本書は新たに「テクニウム(Technium)」という概念を提唱する。テクノロジーが大規模に相互接続されたシステム全体を指し、「自己推進的なニュアンス」「自己強化する創造システム」の概念を含む。
われわれの周りでいま唸っている、より大きくグローバルで大規模に相互に結ばれているテクノロジーのシステムを指すものとして<テクニウム technium>という言葉を作った。
テクニウムはただのピカピカのハードウェアの範疇を超え、ありとあらゆる種類の文化、アート、社会組織、知的創造の全てを含む言葉だ。それには手に触れることのできない、ソフトウェアや法律、哲学概念なども含む。そして最も重要なことは、われわれが発明をし、より多くの道具を生み出し、それがもっと多くのテクノロジーの発明や自己を増強する結びつきを生み出すという、生成的な衝動を含んでいるということだ。
<テクノロジー>の複数形は特許の対象となるが、<テクニウム>は特許システム自体をも包含するものを意味するのだ。
個別のテクノロジーよりもさらに抽象度が高く、包括的なこの概念が、本書の主人公だ。本書によれば、テクニウムの起源であり、テクニウムと我々を繋ぐものが「言葉」である。
原人が現在の人類になった後、約5年前に、彼らの生活様式や文化に大きな変化が見られたという。彼らの脳内に何らかの突然変異が起き、言語が生じたのだ。言語の発明を転換点として、文明の進展は一気に加速する。
本書によれば、言語は個体間のコミュニケーションを円滑にしただけでなく、長寿命化に伴い祖父母世代が孫世代に知識を伝える「おばあちゃん効果」を発生させた。さらには書き言葉が遺ることで、より大きな世代間でのコミュニケーションをも実現した。「知」が蓄積可能になったのだ。
そして本書は、言語の最高の優位性が「自動生成」にあるとする。言語の知的構造を手にすることで、ヒトは自分の精神活動にアクセスでき、「言語は知性に知性自身を問うことができるように」なった。ヒトに生じた知性は、言語を得ることで独立を実現したのだ。

脳内に閉じ込められていた概念は、言葉により形を得、構造化を果たした
(画像はLe Penseur. #paris #rodin by claydevouteから加工)
それでは、言語はいかにして生命とテクニウムとをつなぐのか。著者はまず生命の進化について、生物学者ジョン・メイナード・スミスとエオルシュ・サトマーリの分類を紹介する。これは生命を「自己生成可能な情報システム」と捉えた場合の分類で、生物学的情報の8つの閾値に基づき分けられる。下図のオレンジの部分だ。
「単一の複製する分子」からはじまり、霊長類による「社会」がを形成されるまで、複製される情報の単位が大規模化・複雑化する様子がわかる。

「自己生成可能な情報システム」の遷移(『テクニウム』記載に基づき作成)
一方で上図の青色の部分は、本書がまとめたテクニウムの遷移だ。言葉の発明以降、情報を伝える人間はほとんど変化していない一方で、印刷技術や工業技術などのテクノロジーは「自己生成可能な情報システム」を段階的に成長させてきた。
生命を共通の生化学的設計図をもつ部門でわけると、菌類、植物、動物、そして3種類の単細胞生物の6つの界から成り立つという。本書が主張するのは、生命の進化とテクニウムの発展は「言語」を介して繋がれており、「テクニウムは、生命の六界で始まった情報の再編成をさらに推し進める」というものだ。
本書はこの遷移における「言語」の意味を次のように伝えている。
システム的観点から見ると、言語は遺伝子より早く学習による適応や伝達を行うことができるものだった。
言語の発明は自然世界における最後の大きな変化だが、人工物の世界ではそれが最初の変化だった。
生命を1つの「進化する情報システム」と捉えたジョン・メイナード・スミスらの分類を持ち出すことで、本書は生命とテクニウムとを1つの軸で語ることに成功している。実体のある生命と、概念に過ぎないテクニウムという、一見関係の弱そうな両者が1つの系譜に繋がることは、とても刺激的な主張だった(目からうろこでした)。
しかし、進化の評価軸を「情報」に求めることは、生命とテクニウムとを結ぶためのこじつけにはならないか。評価軸を別のものに変えたら、テクニウムが生命の延長とは言えなくなるのではないか。
ここで、「進化」についての辞書の定義を見てみよう。
生物は不変のものではなく、長大な年月の間に次第に変化して現生の複雑で多様な生物が生じた、という考えに基づく歴史的変化の過程。
三省堂大辞林
生物のゲノムが何世代にもわたって変化し、その結果として表れる形質が選択を受けて別の種や系統に変化すること。
生物学用語辞典
いずれも「生物の変化」がキーワードになっている。この変化が行われてきた方向を考えたとき、ジョン・メイナード・スミスらの仮説である「自己生成可能な情報システム」の発展的変化も、進化が示す方向性の少なくとも1つと言えるだろう。
進化の方向として「自己生成可能な情報システム」の発達が含まれるなら、情報システム自身が遺伝子以上の適応能力・伝達能力を求めてテクニウムになった、という仮説も成り立ちそうだ。
本書は、情報とは「常に」増大し、非物質化・複雑化する傾向にあるという。そして情報システムはやがて情報システムそのものとして存在するようになると予想している。
テクニウムは我々人間の「言葉」から進化を始めたが、同じく言語を持つとされるイルカや、冒頭で紹介したクリボウシオーストラリアマルハシからも、テクニウムは生まれるのだろうか。
私はそれは難しいと考える。少なくとも現状のイルカや鳥では、言語の次の段階である「文字の筆記」へのパラダイムシフトを起こせそうにないからだ。
原始的な言語を獲得したとしても、それを一定水準の知性に高めるためには、脳容積を増やさねばならない。「心」のメカニズムの解明を試みた『フューチャー・オブ・マインド』(2015)では、知性を発揮するために必要になる脳構造を段階的に示しており、拡大した脳容積を支え、発話するには、結局人間と同じような身体的特徴にならざるを得ないと指摘している。
したがって、私はテクニウムが人間に始まったことは必然であると考える。

Human Evolution? / bryanwright5@gmail.com
ちなみにこの「必然」というのは、テクニウムの未来を予想する上で重要な前提となる。
本書はテクニウムの進化を決める要素について、再び生命の進化をアナロジーに分析をする。本書によれば、我々が太古の原子からヒトにまで進化してきたのは必然であり、時間を巻き戻してやり直しても、同じ結果を得ることができるという。進化の原理にはいかなる力が働いているのか、テクニウムの未来を予想することはできるのか、それはいかなる姿なのか。これについて次の記事にて、本書の仮説を紹介したい。
ところで、機械やテクノロジーを生命と対比する手法は、本書のほかに『フューチャー・オブ・マインド』でも見られた。ある事象を最先端科学からのアナロジーとして考えるのはよく行われる手段だ。例えば19世紀のロボットのイメージはブリキと蒸気と歯車で、21世紀の人工知能は人の脳構造を模倣している。
本書や『フューチャー・オブ・マインド』が生命のアナロジーを使うのは、この分野が現在進行形の最先端という背景もあるのだろう。逆に言えば、生命の秘密がいままさに解明されつつあるからこそ、テクニウムの正体や未来を考えられるようになったのかもしれない。