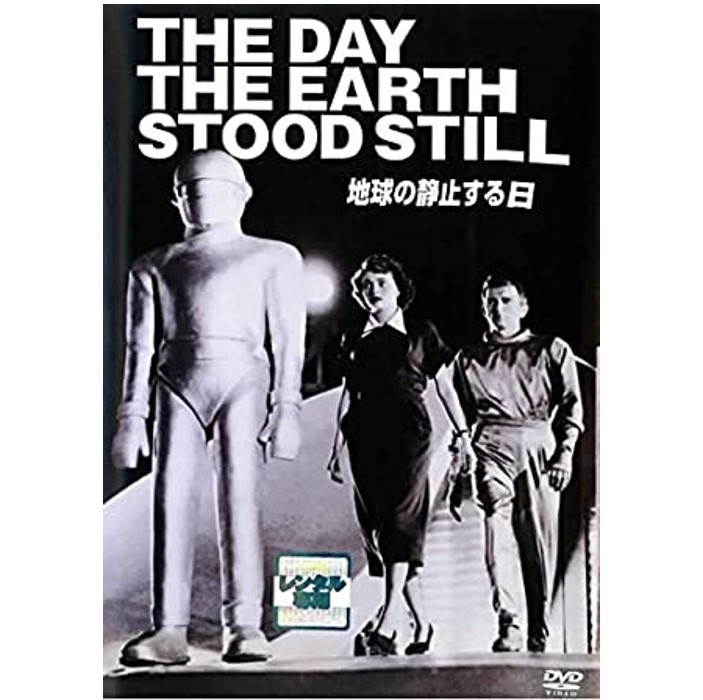いなたくんへ
次のブログの「たった5分で国際関係論を習得する方法」という記事がおもしろい。ハーバード大学スティーブン・ウォルト教授が卒業生向けに書いたブログの翻訳で、「専門学科の学生が卒業から5年経っても覚えている基本概念を5分で読める記事で書く」というコンセプトだ。
- たった5分で国際関係論を習得する方法(地政学を英国で学んだ,2016/1/28)
- 翻訳元記事:How to Get a B.A. in International Relations in 5 Minutes(foreignpolicy,2014/5/19)
基本概念は次の5項目が挙げられていて、本当に5分もかからず読めてありがたい。
- 1.アナーキー(無政府状態)
- 2.バランスオブパワー(勢力均衡)
- 3.比較優位(または貿易の利益)
- 4.認識間違いと計算間違い
- 5.社会構成
1番目で説明される「アナーキー(無政府状態)」とは、現在の国際社会には警察がおらず、無政府状態であるという前提を述べている。一部を抜粋しよう。
●国際政治が国内政治と異なるのは「中央権威が欠如している状態にある」ということなのだが、これはリアリストだけが認めているものではない。
●国際的な場には警察が見回りを行っているわけではないし、どちらが悪いかどうかを裁定を下すような裁判官はいないし、国が訴訟を起こせるような裁判所もなく、トラブルが起こったとしても誰かに110番をかけることもできないのだ(これについてはウクライナ、レバノン、ルワンダの各政府に聞いてみるがよい)。
●国家が互いから身を守るための中央権威が存在しないということは、主要国が自分自身で身の安全を守らなければならないということになり、今後もトラブルの発生に警戒しつづけなければならないことを意味する。
『たった5分で国際関係論を習得する方法』より
「無政府状態」という字面をみると、『マッドマックス』や『北斗の拳』のヒャッハーで無慈悲な砂漠地帯を思い浮かべてしまう。つまり今の世界とは無関係に感じちゃうけど、国家同士の関係を思えばいまも無政府状態なんだよね。こうした国際社会の無政府状態は、恒久的なものなんだろうか。それとも、今後「世界の警察」のようなものが現れることはあるのだろうか。
古典SF映画『地球の静止する日』(1951)では、「世界の警察」が平和を監視するという発達した宇宙社会が描かれていた。前回『メトロポリス』(1927)に引き続きSF映画を観てみたので、今回もその感想と、未来の国際社会について考えてみた。
![地球の静止する日 [レンタル落ち]](http://hiah.minibird.jp/wp/wp-content/plugins/jquery-image-lazy-loading/images/grey.gif)
本作は宇宙人モノ。2008年にキアヌ・リーブス主演でリメイクされたバージョンを思い浮かべる人もいるかもだけど、今回観たのは1951年公開のオリジナル。あらすじはWikipediaから。
アメリカの首都ワシントンD.C.に銀色の円盤が着陸し、人間の姿で奇妙な服を着た男が現れた。彼の名はクラトゥ。自分は宇宙人であり、地球人には危害を加えないと語る。しかし警備兵は彼に向かって発砲してしまう。船体からロボットのゴートが現われ、周囲の武器を破壊しようとするが、クラトゥはゴートを制止した。
彼は大統領秘書に、地球上の指導者たちが核兵器や戦争による殺戮で他の天体の征服を考えるのは、他の星からの攻撃に繋がることを忠告したいと言った。彼は地球人を説得する平和の使者であった。指導者たちが彼と同席することを拒んだため、クラトゥは宿屋に住み街の人々に紛れ込んだ。彼は科学者バーンハート教授と会い、使命の重大さを認識させるために世界中の電気を止めることにする。
しかしクラトゥの意図は誤解され、逮捕命令が出された。軍に逮捕されたとき、彼は致命傷を負ってしまう。クラトゥは使命を果たすことができるのか。
それまで「宇宙人といえば子供向けの侵略者モノ」という先入観があったなか、「本当に宇宙人が来たら何が起こる?」というシミュレーションを初めて行ったのが本作という。
米国の火星人侵略騒動が1938年、世界初の人工衛星スプートニク打ち上げが1957年という時代。宇宙は未知に満ち満ちており「宇宙人来訪をマジメ考えてみる」というリアリティ路線が斬新だったようだ。
冒頭の「ヒュロロロロロロ…プワワワワーン…」という不安な音響、そして現れる帽子型UFOがあまりにベタで笑ってしまったけど、あの不思議な音は当時の(少なくとも庶民にとっての)宇宙に対する感覚をよく表現していたのかもしれない。
古い映画ではあるのだけど、リアルと言えば最近のハリウッド映画よりよっぽどリアルだった。派手な爆発に頼るわけでもなく、UFO来訪後の騒動を、市民にまぎれた宇宙人クラトゥの目で観察していく。
拘束されていたクラトゥは、当局の目を盗んで部屋を借りることになる。世間は凶悪な侵略者のニュースで騒然としている、ことになってるけれど、どこか他人事だったりする。ダイニングに集まり朝食をとる宿屋の面々は、新聞を読んだりラジオを聞きながら「宇宙人、どう思うね?」「怖いわぁ」と雑談がてらに情報交換。テーブルを共にするクラトゥは「やれやれ」と密かに笑い、子供の世話なんかをしてくれる。
クラトゥ役の温かみのある演技もさることながら、ヒロインもまた素晴らしかった。クラトゥに子供を頼みながらも、なんとなくクラトゥにひっかかりを覚えている。その「なんとなく」が本当になんとなくで、具体的な行動や言葉に出すわけでもなく、ちょっとし仕草や表情の中に、それこそ観客の方が「なんとなく」ひっかかる。そうした人と人(というか宇宙人)とのふれあいの積み重ねが、この映画を魅力的なものにしている。


クラトゥ(マイケル・レニー)とヒロインのヘレン(パトリシア・ニール)
はるかに進んだ科学力を持つクラトゥは、終盤で実力行使に出る。地球人に自分の言うことを聞かせるためだ。それで何をしたかというと「30分間全地球の電気を止める」というものだった。何という地味さ…。けれども世界に与えた衝撃は甚大で、電話が繋がらず、街は渋滞だらけで人々はパニック。このことはクラトゥの命を危険にさらすことにも繋がる。
最近のド派手なSFXを見慣れた私としては、静かな演出が一周まわって新鮮だった。確かにこれが現実だったら、デモンストレーションとしての威力は絶大だよね。
もちろんSF描写も盛りだくさんだ。円盤は継ぎ目のない表面がいきなり開き、内部は光とジェスチャを用いたユーザインターフェイス。ポケットから取り出されるダイヤモンド(に見える地球に存在しない鉱石)の通貨。ビームを放ち、絶対に傷つけられない無敵のロボット。宇宙には進んだ文明がひしめき、地球は監視されていたという事実。
ちょっと藤子F不二夫のSF短編の匂いも感じたけれど、藤子先生も本作に影響を受けたのかもしれない。
そして最後に明かされるのは、無敵のロボット・ゴートがクラトゥの手下ではなく、クラトゥさえも監視対象とする「世界の警察」という事実だ。

圧倒的な着ぐるみ感を誇るロボット「ゴート」(左奥)
クラトゥが地球に来た目的は、原子力利用を始めた地球人への警告だった。将来他の星を攻撃する可能性があり、それは看過できないという。
クラトゥは個人ではなく全地球人にメッセージを伝えるため、各国首脳を集めることを要求する。ところが米大統領補佐官の返事と言えば「現実的ではない」の一点張り。一応呼びかけはしたようだけど、「モスクワ開催ならいいけどアメリカには行けないね」という某国の返答が読み上げられる。
宇宙人来訪の事態ですら、各国首脳を同じテーブルにつけることができない。1951年の空気感を改めて感じる一幕だった。当時は朝鮮戦争真っ只中で、世界を二分する冷戦がすでに始まっている。この露骨ないがみ合いに比べると、問題があるとは言え現代はいくぶん平和になったのかな、と思えてしまった。
ところで気になるのは、クラトゥが一体何様の立場で警告に来たのかだ。彼は人類に警告する「世界の警察」に見えて、実はそうではないところがこの映画の巧妙な点。クラトゥや宇宙の星々は、クラトゥに同伴したロボット「ゴート」に宇宙の平和維持を一任していることが明らかにされる。
ゴートは平和を脅かすものを容赦なく滅ぼす(惑星を一瞬で消せる)。クラトゥは善意で警告に来た「隣人」に過ぎない。「こいつ怒らせるとマジやばいよ、君たち調子に乗り始めたようだから忠告するけど、いい加減にしといたほうがいいよ」とわざわざ教えに来てくれたのだ。

ゴートの発する怪光線は劇中で数名の犠牲者を出したが、その気になれば地球ごとやれたようだ
我々の住む地球はいまだかつて、一元的な権力を持つ存在に統治されたことはない。「国際関係論の基本概念」で最初に挙げられた「アナーキー(無政府状態)」にある。独立した国家の集まりが、条約を結んだり、国際組織をつくったり、時には武力を用いることで、何らかの均衡と秩序をつくっている。
『地球の静止する日』の宇宙世界もまた、どうやら同じ状況にあるようだ。圧倒的な力をもつ誰かが世界を支配するのではなく、惑星間は互いに独立した存在である。このことは、惑星間で紛争が起こりうるというクラトゥの言葉から示唆される。紛争が起こりうるからこそ、彼らはゴートという警察を必要とし、また地球が紛争当事国となる未来を警告している。平和を監督する警察がなぜ人ならぬロボットなのか。それは、人の手による平和が実現できなかったからだろう。
我々の世界で、国際社会の無政府状態はいつまで続くだろうか。一元的な権力の出現は起こりうるのか。それは、どこかの国が他のすべての国を支配したり、(失敗しかけてるけど)欧州連合のような緩やかな融和の形で進むだろうか。それとも『地球の静止する日』のゴートのような人工的な統治者が登場することもあるのだろうか。
人工的な統治者で思い出すのは、遺伝子戦争の千年後を描いた名作『風の谷のナウシカ』(1983~)だ。ナウシカの世界では過去に、生命体をも意のままに造り変える巨大産業文明により「調停者」が造られている。巨神兵だ。


「火の7日間」の千年後に目覚めた巨神兵は王をも超える存在として振舞う。
巨神兵の身体には「東亜工廠」の商標が刻まれている。
(徳間書店『風の谷のナウシカ』7巻より引用)
巨神兵は「ありとあらゆる宗教、ありとあらゆる正義、ありとあらゆる利害」の調停を目的とした人工の神である。人同士の争いを諌める人外の存在、という意味では、巨神兵はゴートと共通している。
遺伝子技術の進歩の速さは、ナウシカの世界が決して空想に留まらないことを予見させる。ゲノム編集技術は着実に世代を進めており、遺伝子の操作はより正確に、より高度に実現できるようになっている。一方ソフトウェアについてみると、人工知能の進化はまさに日進月歩だ。こうした技術が発達を続け、特異点を超える日は決して遠いものではない。
そのとき私たちは、「調停者」を作り上げ、秩序の維持を任せるだろうか。
WIRED創業編集長ケヴィン・ケリーの『テクニウム』(2014)は、生命の進化とテクノロジーの進歩とをひとつの軸に重ね、その進化の先を予想した一冊だ。『テクニウム』では、「法」もまたテクノロジーの1つであると述べている。
ウェンデル・ベリーが同意してくれそうな答えは、法律のテクノロジーは人を良くしてくれたということだ。法律の体系によって、責任、公平さが保証され、望ましくない衝動を抑え、信頼を育てることができる。ヨーロッパ社会の底辺を支える法律の入念なシステムは、ソフトウェアの世界とあまり変わらない。コンピューターではなく紙の上に複雑なコード体系が書かれているだけで、ゆっくりと公平さや(理想的な)秩序を計算している。
『テクニウム』より
無政府状態とされる国際関係であるが、いまある秩序は長い進化を経てたどり着いたものだ。ウェストファリア条約、共産主義体制、国連、核兵器の相互確証破壊など、社会を安定させる様々な「発明」が試され、改良されてきた。時間はかかるかもしれないが、我々がまだ経験しない、想像したこともない国際関係の在り方が、これからの世界で発明される可能性は大いにある。それもまたテクノロジーの1つなのだ。
ゴートや巨神兵といった、人を超越した統治者をテクノロジーが生む可能性はあるだろう。その一方で、テクノロジーは国際社会の関係性を規定する別種の方法論を出現させることもある。
我々の世界が『地球の静止する日』のクラトゥの宇宙に向かうのか、それとも、映画では描かれなかった別の秩序が現れるのか。どちらが良いのか、あるいは変化することが好ましいのか、現時点ではわからないが、今後起こる世界の変化に期待したい。